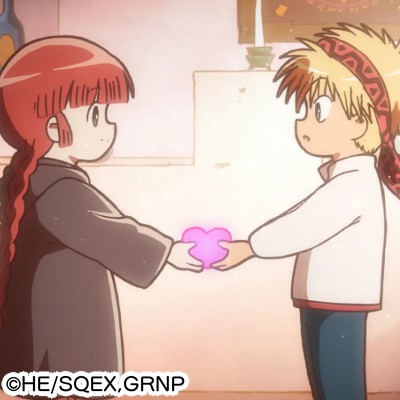幻魔特区 RELOADED Story1【黒猫のウィズ】
白猫ストーリー
黒猫ストーリー
| 2017/00/00 |
目次
story0 プロローグ
うららかな午後の日差しを浴びながら、君とウィズはまどろんでいた。
ギルドから依頼されていた仕事を一気に片づけた反動だろうか。強烈な睡魔に襲われていた。
といって、特に抵抗する必要もない。
睡魔を素直に受け入れ、深い眠りの淵へ落ちようとしていたそのとき――

”カムラナ技研工業より特殊認証コードを受信しました。ご返答をお願い致します。
小箱のような機械〈フォナー〉から音声が発せられている。
君と同じようにうとうとしていたウィズが飛び跳ねるように目覚める。
「フォナーにゃ!すごく久しぶりに喋ってるにゃ!」
興奮したウィズがフォナーを取り出そうと君の懐をまさぐっていると――
”〈承諾〉ありがとうございます。あなたの再訪を歓迎します。”
「にゃにゃ!承諾しちゃったっぽいにゃ!
懐からフォナーを取り出す間もなく君の視界は揺らぎ、意識が薄れていく――
***

そこは木々が鬱蒼と生い茂る、静謐な森だった。
かつて訪れたことのある異界である。
見知った顔や場所が目の前にあれぱと期待していたが、そううまくはいかないらしい。
「ここでぼーっとしていても仕方ないにゃ。人のいるところに行くにゃ。」
君はひとまず、この異界の象徴とも言える〈ロッド〉を探す。
巨大な塔のようにそびえるロッドの周辺に人が集まり、街が形成される異界である。ロッドに向かっていけば、誰かに会えるはずだ。
しかし視界は生い茂る木々に遮られていて、遠くまで見渡すことができない。
まずは森を抜ける必要がある。出口を探して、君は歩き出す。
「それにしても、この異界は猫が喋っても変な目で見られないから安心にゃ。」

この異界の人々は自らの心の分身である〈ガーディアン・アバター〉と共に戦う。
アバターの中には人の言葉を喋るものも存在しているため、ウィズが人々から奇異の目で見られることもないのだ。

人々――そうひと口に言っても、この異界には人間と、人間によって製造された〈ガーディアン〉がいる。
かつて君が共闘したのは、世界中にあるロッドを守るために作られた存在であるガーディアンたちだった。
君がかつての冒険に想いを馳せていると、ウィズにそっと小突かれた。
「普通の森という感じではないにゃ。キミ、気を引き締めるにゃ。」
君は師匠の忠告に従い、カードを構えて周囲の様子を窺いながら歩を進める。
耳を澄ませながらしばらく歩いていると、微かな足音が聞こえた。
獣のそれではない、人間のものだ。昼下がりの散歩を思わせるようなゆったりとした、どこかけだるそうな足取り。
やがて足音が止まった。
逡巡した後、君は足音が聞こえた方へ向かう。
葉陰に身を潜めながらそっと様子を窺う――

「んん……。」
大樹に寄りかかるようにして、うつらうつらとしている少年がいた。
その傍らには、ぐでーっと寝そべる仔犬がいる。
ぴくりと耳を動かした仔犬は君とウィズを一瞥すると、

「あう……。」
けだるそうに鳴いて、前脚で少年の膝を叩いた。
すると少年が目を覚まし、君たちに気づく。

「うお、びっくりした。急に出てくるなって。魔物かと思った。」
言葉とは裏腹に、少年の声音はのん気に間延びしていた。
君は驚かせてしまったことを詫び、敵意がないことを伝える。
「まあ、そうだろうなー。お前のその格好を見る限り。
少年はのっそりと立ち上がり、君のまとっているローブを指でつまむ。

「英雄に憧れて、こんな格好してるんだろ?」
「英雄……にゃ?」
「おおー、しゃべる猫まで完璧に再現してるのか。英雄譚に出てくる黒猫の魔法使いのこと、相当好きなんだな。」
「黒猫の魔法使いって……私たちのこと知ってるにゃ?でも、英雄譚ってなんにゃ?」
どうも話が見えてこない。
まあそれはいつものことかと思い苦笑していると、少年は感心したように君の顔をまじまじと見つめる。
「わかるわー、その困ってるっほい笑い方。本物の魔法使いも、そういう感じだったらしいね。」
なかなか似てるでしょ?と君は話を合わせておく。

「おれの名前はレグル。700号ロッド自警団のメンバーだ。
こいつはおれのガーディアン・アバター、シロ。」
「あぅ、あーぅう。」
状況が飲み込めないまま、君はレグルと握手を交わした。
story1 700号ロツド自警団心得

タイシは700号ロツド自警団第2小隊長である。
自警団として魔物退治に励む傍らで、集落の子どもを捕まえては英雄譚を語って聞かせるのがライフワークだ。
大きくなったら自警団に入りたい――そう思う子どもがひとりでも増えてほしい。
そのためには、英雄とまではいかないまでも、自警団のメンバーは子どもが憧れるような存在でなければならない。
魔物を寄せ付けない頼もしい力と、英雄の意志を継ぐ正しい心。それこそが、自警団に必要なものだ。

「ファルサ。」
「なあに?あたしはあんたと違って忙しいの。話があるならさっさとしてくれないかしら。」
「君は自警団に所属する身でありながら、英雄たちの意志を継ごうとせず蔑ろにしている。」
「英雄なんてどうだっていいじゃない。魔物を殺せばいいんでしょ?」
「そんな心構えじゃ困る。これから自警団を目指そうとする子どもたちにも示しがつかない。悪影響だ。」
「悪影響、ねえ。あんた、自分が子どもたちに陰でなんて呼ばれてるか知ってる?」
ファルサは唇を歪ませてにたりと笑う。
「英雄オタクのウザにーちゃんですって。」
「ぐっ……僕はただ、未来に受け継ぐべき英雄譚を語り聞かせてるだけなのに。」
「まあ、子どもは素直だから仕方ないわね。あたしだって、ひどい呼ばれ方されたもの。」
「……なんて?」
「アレな人。」
「子ども素直だな!」
「そう、子どもは素直。面と向かってあたしにそう言ってきたから、誤解をといてあげたわ。
そうしたら、会うたびにあたしのこと『優しいお姉ちゃんもうやめてください』って呼んでくれるようになったの。」
「なにやったか知らないけど痕跡残ってるぞ。」
「で、なんの話だったかしら。シメるなら痕跡を消せという話?」
「自警団として活動するにあたり、先人の偉業をちゃんと知っておけという話だ。」
手の焼ける団員に呆れつつも、タイシは切り口を変えて英雄に興味を持たせようとする。
「ファルサこそ、キワムに感謝するべきなんだ。キワムがいたからこそ、ファルサは自警団として活動できるのだから。」
「キワム? あんたのお気に入りの英雄だったかしら。」
「昔、悪いやつの手から世界を守って、人間とガーディアンの橋渡し役になったんでしょ? そんな歴史、あたしには関係ないわ。」
「僕たち人間がガーディアンと同様にアバターを召喚できるようになったのは、誰のおかげだ?」
「それはわかるわ。ウシュガ博士でしょう? ものすごい変人って噂ね。会ってみたい。」
「そう。途轍もない力と引き換えに身体を蝕む〈コイン〉を改良して、僕たちでも安全に使えるようにしたのはウシュガ博士だ。
ウシュガ博士はかつて〈収穫者〉のひとりとして世界に危機をもたらした。
キワムたち英雄が収穫者と戦い、その野望を阻止したからこそ、今があるんだ。
もしもキワムがいなければ、コインの改良はなされなかったわけで、ファルサは魔物と戦うこともできなかったというわけさ。
これで少しは英雄譚が身近に感じられたかな?魔物と戦うのが好きなファルサこそ、英雄に感謝しないと。」
「でも、それを言い出したらあたしはカリュプスに感謝しなくちゃいけないわ。魔物ってカリュプスの分身体なんでしょう?
うまく丸め込もうとしたら、屁理屈で返された。
千年以上前に突如この星に襲釆し、文明を崩壊寸前にまで追い込んだ謎の巨大生命体、カリュプス。
確かに、カリュプスがすべての起源とも言える。
この世界の中心となって久しい各地の大ロッドはカリュプスを封印するためのものだ。
ガーディアンにしても、その製造にはカリュプスの体液〈C資源〉が使われている。
タイシが憧れてやまないキワムも、カリュプスがいなければ存在しなかったというわけだ。
「いや、でも、さすがにカリュプスに感謝はないって……。」
「カリュプスだけじゃないわね。カリュプスにとどめをささずに有効活用した当時の人間にも感謝しないと。
これじゃ感謝する相手が多すぎるわ。」
「……それが歴史というものだよ。」
「なにそのキメ顔。これがいわゆるウザにーちゃんってやつね。」
「とにかく、英雄への感謝を忘れず、正しい心を持って活動に励もうじゃないか。ひとりひとりの意識が大切だ。」
「でも、うちの自警団にはあのバカみたいに強い子がいるじゃない。ひとりひとりの意識がどうこう言われても、説得力がないのよね。
あたしは日陰でひっそり、魔物を血祭りにあげるだけよ。」
「……ひっそりなら祭るな。」
story2

「お前……やっぱ本物の英雄? 強いなー。」
君の魔法を見たレグルは目をしばたかせている。
「もっかい握手してくれ。シロも、ウィズと握手してもらえ。」
「ばあーう。」
シロはウィズに向かって右前脚を差し出す。ウィズは何とも言えない表情で右前脚を突き合わせた。
「ついでにお願いなんだけど、本物の英雄として、テーラにちょっと言ってくれよ。全然おれら人間と仲良くしないんだ。
あいつ、自分ひとりで北の森を全部守るから、人間は集落の南側を守れって言ってさ。
実際ひとりで守れてるのがすごいんだけど、それってどうなのかなーって思って。協力したほうが安全だし。」
「人間と馴染めないガーディアンもいるってことなのかにゃ。」
人間にもいろんなタイプがいるように、ガーディアンも十把一絡げではないということだろう。
「ところで、どうしてレグルはテーラの持ち場に来たにゃ?」
「聞いたんだ。〈声〉を。」
レグルは胸に手を当て、すっと目を閉じる。
「たまに聞こえるんだよね、よくわかんない謎の〈声〉が。
今日も昼寝してたら聞こえてきてさ。「森」「森」ってうるさいから、来てみたってわけ。」
「それ……ただの夢にゃ?」
レグルはふざけているふうではなかった。
「夢じゃないって。その証拠に、この魔物だよ。
毎日テーラが森で退治した魔物のデータを自警団にレポートで報告してるんだけどさ。」
「律儀にゃ。」
「テーラのレポートと比べると、今日は数が多いし、凶暴な気がする。いくらあいつが強くても、ちょっと心配だなあ。」
「心配だったらもっときびきび動くにゃ。英雄と握手なんてしてる場合じゃないにゃ。」
ウィズがレグルにお説教をしていると、相手を威嚇するような魔物の奇声が聞こえた。
君とレグルは一瞬顔を見合わせた後、音が聞こえたほうに向かって走った。
***
駆けつけた先で、少女が魔物に囲まれていた。
「テーラ! 大丈夫か!?」
テーラと呼ばれた少女は銃で魔物を牽制しながら、冷たく鋭い視線をレグルに向ける。

「レグル……こんなところまで何しに来たの。危ないから帰って。」
「危ないのはどっちだ。苦戦してるじゃないか。今助ける!」
「これが苦戦してるように見えるの? ……節穴。戦いながら敵のデータを取ってるだけ。」
「強がるなって。たまにはおれも仕事するよ。」
「強がってない。邪魔しないで。」

『確かに苦戦こそしていませんが、敵に異常が見られる以上、どう転ぶかわかりかねます。人員が増えるに越したことはないですぞ。』
テーラの足元にいる小さな機械の人形が言った。
おそらくあれがテーラのガーディアン・アバターなのだろう。
「ロイド、余計なこと言わないで。私ひとりで十分だから。」
「ロイドはわかってるなあ。よーし、シロ、いくぞ。」

「我が心に眠る戦獣よ、救世の星となれ!¨サルヴァトル¨!」
レグルの詠唱によってシロが光を放ち、巨大な鈎爪を持つ獣サルヴァトルヘと変身を遂げた。
それは硬質の実体であるような、まばゆい幻影であるような、なんとも掴み難い不思議な存在だった。
そしてレグルがサルヴァトルをまとうように、あるいはサルヴァトルがレグルを守るように、主従は一体化する。
「200年ぶりってことは、魔法使いはこれ知らないんだっけ?」
君に向かって手を振るように、レグルが巨大な鈎爪を掲げてみせる。
「〈ガーディアン・アーマー〉っていう新しい技術だよ。早い話が、アバターが武器と鎧の役割を果たすんだ。」
「我が心の正義よ、惑わずただ其れを為せ!¨ユースティティア¨! 」
テーラの詠唱によってロイドが光を放ち、重兵装の機械人形ユースティティアに変身する。
あれもガーディアン・アーマーなのだろう、主従が一体化した形態となった。
新たなガーディアンの技術に圧倒されながら、君も力―ドに魔力を込めて戦闘態勢に入った。
***
テーラを囲んでいた魔物たちはひと際凶暴だったがー―
「うおりゃっ!」
サルヴァトルをまとうレグルが巨大な鈎爪を振るっていき、片っ端から魔物を倒していく。
服物の頑丈な外殼をものともしない、鋭い斬撃だった。
レグルが倒しそこねた魔物は、ユースティティアをまとうテーラの正確無比な射撃が逃がさない。
援護に回った君は防御障壁を即時展開できるよう準備していたが、ガーディアン・アーマーを操るふたりは危なげなく魔物を殲滅した。
抜群のコンビネーション……のように見えたが、テーラはどこか苛立たしげだった。
「魔物に異変が起きていることは明らか。亡骸を調べる必要があったのに、こんなに派手に切り裂いて。」
「……。え、あー、ごめん。でも、テーラが無事でよかったよ。」
「この程度の魔物相手にやられるはずない。あなたとー緒にしないで。」
テーラはため息をつき、地面に横たわる魔物の亡骸を見回す。
「こいつは外傷が少ない。銃創がひとつだけ。」
テーラが近づいたそのとき、魔物がぴくりと体を震わせた。
「ひあっ!」
悲鳴をあげて尻もちをついたテーラは、魔物目がけて銃を乱射した。
「ははっ、びっくりしてる。テーラも結構ビビりだなー。」
「……うるさい。」
「調べなきゃいけないのに、跡形もなくふっ飛ばしちゃったよ。」
「……もう調べ終わった。ひと目見れば大体わかる。」
「にゃはは。冷たい子だと思ったら可愛いところもあるにゃ。」
テーラがぎろりとウィズを睨み、君へと視線を移動させる。
「そうそう。見ろよ、英雄譚に出てくる黒猫の魔法使いだ。テーラも握手してもらえよ。」
「本物がこんな辺境にいるはずない。どうせ、真似してるだけ。」
「本物だって。テーラと同じくらい強いかも。いや、英雄だし、テーラより強いんじゃないか?」
テーラが値踏みするような目で君を見る。
そんな大層なものじゃないですよと君は否定の姿勢を見せる。
「……腰抜け。」
「腰抜かして尻もちっいたやつが言うかねー。ケツにめっちゃ泥っいてるし。」
「……私は引き続き調査を進める。あなたたちは邪魔だから集落に戻って。寄り道せず、まっすぐ。」
テーラは尻についた泥をばしばしと手で払ってから、立ち去っていった。
「なかなか気難しい子にゃ。」
「そうなんだよ。気難しい。」
「あと、レグルもひと言多いにゃ。ちょっとデリカシーがないにゃ。」
「そんなことより、魔法使いの歓迎会をやらないとな。」
「そういうところにゃ。デリカシーもなければ危機感もないにゃ。」
ウィズもわりとデリカシーと危機感ないよね――君はそんな思いを胸にしまっておく。
「見慣れない魔物が現れたから、自警団として連携を高める必要がある。
そのためには、宴だよ。堅苦しい作戦会議をやっても、頭に入ってこないじゃん。」
「宴なら入ってくるにゃ?」
「入るよ。仲間と食べるうまい飯は、いくらでも入る。」
「ご飯の話になってるにゃ。……とはいえ、英雄として、歓待を受けるにやぶさかでないにゃ。」
story 第2小隊
君とウィズの歓迎会は、宴というには実にささやかなものだったが、料理は見事だった。
なかでもロッドの農園で採れたという野菜や果物はどれも新鮮で、素材の味を活かした料理は君の舌を楽しませてくれる。
料理に舌鼓を打っていると、レグルから同じ小隊だというふたりを紹介される。

まずは、猛禽のアバターを連れた、長髪の凛とした青年が自己紹介をする。
「僕は、タイシ。こっちはタカノハ。」
タイシの腕におとなしく止まっているタカノハが低く唸る。
「700号ロッド自警団の第2小隊長をやってる。好きな英雄はキワム。
君が好きなのは……ははっ。その格好を見ればひと目でわかるね。いろいろ話そうじゃないか。よろしく。」

続いて、毒々しい植物のアバターを従えた少女がニコリと微笑む。
「あたしはファルサ。この子はキルキル。かわいいでしょう?」
ファルサは奇妙な植物キルキルをつつく。
「集落の子どもたちからは『優しいお姉ちゃんもうやめてください』って呼ばれてるわ。」
「それを自己紹介に使うのか……。」
「つまり優しいってこと。よろしくね。」
君は簡単に自己紹介をする。
やはりというべきか、英雄譚に出てくる黒猫の魔法使いの真似をしている旅人という認識を持たれてしまったようだ。
「あとはテーラが第2小隊なんだけど………やっぱり来ないか。」
森から戻ってきたテーラも誘ったらしいが、反故にされてしまったようだ。
「ほんと付き合い悪いわね、あの子。あたしたちのことを仲間だと思ってないんだわ。
きっと自分ひとりでなんでもできると思ってるのよ。そういうとこ、憧れちゃう。」
「今の流れで憧れ!?」
「おれも自分ひとりでなんでもできるようになりたいなー。
「そしたら、自分のベースで生きられる。好きなだけ昼寝もできる。」
「今もそうしてるじゃないか……。」
タイシは嘆息して、肩をすくめてみせる。

「とまあ、うちの小隊はこんな感じなんだよ。揃いも揃って協調性がない。」
「小隊長の仕事、大変そうにゃ。」
「英雄を目指すからには、仲間と助け合う気持ちが大事なのに。」
タイシがぼそりとこぼした言葉に、レグルとファルサが反応する。

「別に英雄目指してないよ。おれは自警団で十分だ。」
「そうよ。あたしだって魔物を殺せればそれでいいもの。
最低限の衣食住に、大胆な殺戮。それで十分幸せよ。」
「魔物退治を殺戮って言うな。」
「むしろ自分の夢を周りに押し付けるタイシが一番協調性がないわね。」
「まあそう責めるなよファルサ。タイシだっていろいろ疲れてるんだろうし。多少のわがままくらい聞いてやるのが仲間ってもんだ。」
「完全に僕が悪いみたいな流れ……しかもみんな、多少のわがまま聞いてくれてないよね?」
君とウィズは苦笑するしかない。
「常識人がタイシしかいないみたいにゃ。タイシもタイシで若干怪しいところがあるにゃ。
もしかしてテーラは、勝手すぎる小隊のメンバーに嫌気がさして単独行動をしてるのかもしれないにゃ。」
「テーラも負けないくらい勝手なんだから。自分ばっかりたくさん魔物殺して。
他人のことを考えないずうずうしい女よ。ほんと憧れちゃう。」
「さっきから憧れ方がおかしいんだよ。」
「あたしの獲物をとらないでほしいわ。テーラに横取りされないように、魔物の額に焼き印押して回ろうかしら。」
「焼き印押すタイミングで殺せよ。いや、そういう問題でもないけど。」
「あんまり欲張るようなら、しまいにはテーラのことを殺すわよ。そのときはレグル、手伝いなさい。」
「え一、ファルサの味方すると人格を疑われそうだからやだなー。」
「その通りなんだけど、人からの評価を気にするなら普段からもっとちゃんとしよう?」
「そんなことより魔法使い、食べてるか? 肉食え肉。肉は魔力の源だ。」
肉が魔力の源になる実感はないが、君は取り分けてもらった肉料理を食べる。
「肉っていいわよね。命を喰らってる感じがあるもの。ほら、もっと肉食べなさい。」
ファルサが食べきれないほどの肉を君の取り皿に盛る。
「ここにテーラが加わる……まとまる気がしないにゃ。」
君も、さきほどの気難しげなテーラが小隊の仲間たちと談笑している様を想像してみる。
が――うまく像を結ばなかった。
story 止まった時間

森。
〈声〉は確かにそう言った。それに従い森を調べると、異常な魔物が出現した。
謎の〈声〉は妄想や幻聴の類ではなく、何者かによるメッセージなのかもしれない。
テーラはそう思う。
「ちがう、そう思いたいだけ。」
森の一件は偶然で、〈声〉はやはり幻聴なのだ。
過去から逃避するために幻聴を生み出すとは、どこまで弱いのだと自分に呆れる。

『ふたりでいるのに独り言とは、つれないですな。』
「まさか、ロイドが〈声〉の正体だったりして。」
繰り返し何度も聞こえる「よく守った」という〈声〉。
仮にロイドが〈声〉の主だったとして、それは自己正当化のための現実逃避に過ぎない。
自分の心の分身が、自分にとって都合のいい言葉をかけていることになるのだから。
「そういう意味では、ロイドとのお話も独り言なのかな。」
『一理あります。というわけで、自分とばかり話していないで、自警団の皆さんと交流を持ってはどうですかな?』
「腑抜けは嫌い。」
『レグル氏ですか。昨日はしっかりしていましたぞ。あの戦いぶり、元神童の片鱗が見えましたな。』
そういえば、前にレグルも不思議な〈声〉の話をしていた気がする。
自分と同じ〈声〉を聞いているのだろうか。
「いや、違う。絶対違う。」
たしか、昼寝をしているときに聞こえると言っていた。それは夢だろうと一笑に付した覚えがある。
レグルは昼寝が好きだという。昼寝こそが人生で一番気持ちいいことだと言っていた。
その感覚は全く理解できなかった。
人間同様、ガーディアンにも快眠という概念と実感はある。
しかしテーラの場合、そんな感覚機能はカスタマイズの際に切ったし、残していた時分でも、昼寝に対する快感というものはなかった。
だいたい、このロッドで毎日のように昼寝をしているのはレグルだけだ。きっとレグルが特別変わり者なのだろう。
「ロイドは昼寝ってする?」
『自分はこう見えて、昼寝の達人ですぞ。5分の睡眠が30分に感じる昼寝の奥義をマスターしましたからな。』
身近なところに、変わり者がいた。
『厳しいことを言いますが、レグル氏の昼寝はてんでダメです。
長いこと眠って気持ちいいのは当たり前。いかに短い時間でたっぶり寝たと錯覚するか。それが奥義の奥義たる所以なのですから。』
「よくわからない。5分は5分だよ。」
『テーラは時間に正確ですからな。時間に縛られ過ぎている、とも言えますが。』
なかなか皮肉なことを言う。
テーラは愛用の懐中時計を見つめる。
愛用、というのもおかしな話だ。
8時36分52秒。
時計はその時間で止まっている。修理に出すこともできるし、捨てることもできる。
しかし、この時間のまま止めておきたかった。それは、止まった時間に縛られていると言えるのかもしれない。
『おっと、噂をすれば、というやつです。』
なにやら包みを手にしたレグルがゆったりとした足取りでやってきた。

「魔法使いの歓迎会やるって言っただろ。どうして昨日来なかったんだよー。」
「参加するって返事をしたおぼえはない。」
「まったく。歓迎会の料理のあまったやつ、持ってきたから一緒に食べよう。」
レグルが手にした包みを得意げに掲げて見せる。
「チキンの香草焼きだぞ。870号ロッド産の地鶏だってさ。」
「ありがとう。さっそく食事にするから、帰って。」
「一緒に食べるからうまいんだろうに。」
「ひとりでもおいしいから。」
その中でも、食事は絶対ひとりと決めているレグルは含みのある笑いを浮かべる。
「テーラの戦ってるところと食べてるところは、見てて飽きないんだよなー。」
テーラは日常生活から戦闘任務、なにをするにも単独行動を好む。その中でも、食事は絶対ひとりと決めている。
なぜか。
おいしいものを食べると、バカみたいにうれしくなってしまうからだ。
たぶん自分は食糧難の地域で活動することを想定して設計されたガーディアンなのだと思う。
おいしいと感じる間値がものすごく低く設定されているのだろう。どんな料理を食べても、笑みがこぼれてしまう。
それを見られるのがたまらなく恥ずかしい。
おいしい料理は嫌いだ。おいしすぎてびっくりする。食事なんてその辺に生えている野草で十分だ。
「テーラは強情だからなー。とりあえず今日は帰るよ。」
レグルがすごすごと帰っていく。しかしテーラは警戒を解かない。念には念を。
「ロイド、見張って。」
『やれやれ、承知しました。』
安全を確保。
どこか神聖な気持ちで地鶏にナイフを入れ、そっと口に運ぶ。

「ああ……おいしい……。」
なにを食べてもおいしいと感じるが、おいしいものを食べればすこぶるおいしく感じる。
これは、すこぶるだった。
「お一、相変わらずいい笑顔だなー。」
木蔭からレグルが顔をのぞかせていた。
「レグル!? ロイド、どうして!」
『自分はしっかり見張っておりましたぞ、テーラの幸せそうな笑顔を。』
テーラは森の奥へと走り去る。しっかりと、地鶏を携えて。
story中級 森の異変
君は散歩しながら、700号ロッドの澄んだ空気を味わう。
クエス=アリアスでも、これだけ空気のおいしい土地はなかなかない。
「あら、魔法使いと猫。こんにちは。」
色とりどりの花を手にしたファルサに会った。
「きれいな花にゃ。
「当たり前じゃない。あたしがきれいな花だけを選んで摘んだんだから。よかったらどう?
「もらってもいいにゃ?
「ええ、どうぞ。摘んだはいいけど、使い道なんてないし。
「だったらなんで摘んだにゃ?
「お花を摘む理由? そんなの、お花を摘みたいからに決まってるじゃない。猫って馬鹿なのかしら。
「……キミ、あとは任せたにゃ。
君はファルサから花を受け取った。
この辺は自然がいっぱいでいいね。君がなんとなくファルサに尋ねると――
「これもきっとキワムたちのおかげだと思うんだ!
タイシがキワムのことを褒めながら現れた。
「呼んでもないのに出たわね英雄オタク。いい加減英雄譚なんて卒業しなさいよ。
「卒業なんてないよ。な、魔法使い!
「完全に同類だと思われてるにゃ。
「この地は、昔から緑に恵まれていたというわけではないんだ。
緑化が始まったのは、キワムたちが世界を救ってから、5年後のこと。
学者の間では諸説意見がわかれてるけど、緑化はうちのカリュプスなりの人類とのコミュニケーションだって説が有力だ。
きっと、キワムの想いがスサクロッドのカリュプスに伝わり、そこからさらにガルデニアロツドのカリュプスに伝わったんだ。
ガルデニアロッド。
番号ではなく固有名がついているということは大ロッドだろうか?
君は思い出す。
この異界の各地には,カリュプスを封印する大ロッドが点在していると聞いた。
なるほどこの見慣れぬ土地はスザクロッド統治域ではなく、ガルデニアロッド統治域なのだろう。
「こんな無駄話をしている場合じゃなかったわ!
ファルサが悲鳴のような声をあげた。
「さっきストレス解消のために花をぶちぶち引きちぎってたんだけど、森の様子がおかしかったのよ。
「それが花を摘んでた理由なのかにゃ……。
「レグルたちがこの前遭ったっていう変な魔物がいるかもしれない。早くみんなで殺しにいきましょ!
ファルサと想いを同じくしているのか、キルキルも口をパクパク開閉している。
「殺したがりのわりに、仲間を呼んでくる余裕はあるのにゃ。意外と冷静にゃ。
「あたしは徹底的に誰かを虐げたいだけ。生きるか死ぬかなんてまっびら。絶対、大往生するんだから。
その点、テーラはどうかしてるわね。命が惜しくないのかしら。あたしよりもよっぽどいかれてるわよ。
やっぱりがーディアンって、人の心がないのかもしれないわね。
ファルサの言業を聞いたタイシの表情が険しくなる。
君としても、聞き捨てならない発言だった。
「おい、そんな言い方はないだろう。
「どうしてよ。あたしはあの子に聞いたのよ、ひとりで戦って怖いでしょう、一緒に戦いましょうって。
それなのにダンマリのシカトよ。なんて自分勝手なのかしら。そういうとこ、好きなのよね。
「この流れで好き!?
「好きよ。だって面白いじゃない。あんたなんかよりよっぽど面白いわよ。
でもタイシのそういうあんまり面白くないとこ、好きよ。
「反応に困ること言うな!
ファルサは髪をかきあげ、誇らしげに胸を張る。
「あたしは努力家なの。周りの人のことをなるべく好きになるよう、日々頑張っているわ。
ファルサの流し目が君をとらえる。
「魔法使い。あんたの「こいつとはあんまり深く関わりたくないな」って佇まい、好きよ。
それはどうも、と君は軽く会釈して、一歩退いた
「猫も、所詮は猫でしかないところ、好き。
「もはや意味がわからないにゃ。あと私は猫じゃなくてウィズにゃ。
「でも、寝ている誰かを起こすのだけは大嫌いね。反吐が出るわ。
あたし、将来家庭を持ったら絶対旦那よりも子どもよりも遅く起きるって決めてるの。
というわけで魔法使い。昼寝してるレグルを起こしてきなさい。みんなで魔物全殺しの冒険に出発よ!
story3-2
森は、つい先日足を踏み入れたときとは様変わりしていた。
奇妙な植物が異常な速度で繁茂している。
「一体どうしちゃったのかしらね。怖いわ。
言葉とは裏腹に、ファルサは喜色満面の笑みを浮かべている。
「魔物、この前よりヤバくなってるかもなー。
レグルは先はどからずっと眠そうにしている。
昼寝が足りなかったのだろうか。といっても、もう夕方だが。
「みんな、緊張感がなさすぎるよ。油断していると、致命傷を負わされるぞ。
今のところ、襲い掛かってくる魔物たちは小型ばかりで、さしたる脅威ではなかった。君も簡単な攻撃魔法しか使っていない。
とはいえ、先日よりも凶暴化しているのは確かだった。
そしてなにより、森の変わりようである。
見たこともない奇妙な植物が、森全体に広がっている。
大地の緑化はカリュプスの意志によるものだろうと、先ほどタイシが言っていた。
であるならば、森の異常にもカリュプスが関係しているのだろうか?
「キミ。もしかしたらこれはとんでもないことの前兆なのかもしれないにゃ。
ウィズが君に耳打ちする。
「私たちは異界の歪みに呑まれてここに来たわけじゃないにゃ。フォナーに呼ばれてここに来たにゃ。
私たちがここにいるということには、必ず意味があるはずにゃ。
ウィズの言う通りだ。
自分たちがいまこの場所にいることには、何らかの意味がある。
ならば、すべきことを考えた上でそれを為さねばならないだろう。
この場合、自警団と協力して魔物を退治するということが為すべきことだ。
君は改めて力―ドに魔力を込め直す。
その気合が伝わったのか、君の隣を歩くタイシがすごくいい笑顔を向けてくる。
「英雄の風格、出ているな。僕も負けていられない!
我が勇敢なる心よ、英雄の意志を継げ!¨フォルティズ!
タイシの詠唱によって、タカノハが光を放ち、刃のような鋭い羽を持つガーディアン・アーマーになる。
「なによ、いきなり本気出して。あたしの獲物をとるつもり!?
虐げ、奪い、潰す、我は心より笑う!¨リススレニズ!
タイシに対抗するようにファルサも詠唱。
「さあ、魔物たち!早く殺されにきなさい!
キルキルが光を放つと、見るだに恐ろしい食虫植物のようなガーディアン・アーマーとなり、ファルサを包み込むように一体化する。
「みんなすごいやる気だなー。英雄ってのは周りにもいい影響を与えるもんなのか?
「レグルも少しは影響受けてほしいにゃ。
レグルはのそのそとシロを抱きかかえ、どうする? やるか? と話しかけている。
「……ん? なにか聞こえないか?
レグルの発言で、一同が黙って耳をそばだてる。
草木をなぎ倒しながら、なにかがすごい勢いでこちらに向かっているー-そんな音だ。
果たして現れたのは、ひと際大きな魔物と、それを追うテーラだった。
「大物をあたしにプレゼントしてくれるの?意外と仲間想いなのね!
「ひとりで十分だから下がってて!ここは私の持ち場!
「ひとりで仕留められなかったから、おれたちのほうに魔物が突つ込んできたんじゃないか!
「あたしに殺させなさいよ!
「でかいな……みんな! 構えろ!」
もっと気を引き締めるにゃ。
story3-3
君の魔法、そしてガーディアン・アーマーを身にまとったレグルたちの猛攻により、ひと際大きな魔物を倒すことができた。
しかしその断末魔が呼び水になったのか、次々に新たな魔物が現れ、君たちに襲い掛かる。
「ここじゃ同士討ちになりかねない! 開けた場所に敵をおびき寄せて戦おう!
タイシが声を張り上げた。それに対し、ファルサが顔をしかめる。
「命令しないで! あたしにはあたしの戦闘プランがあるんだから!
「じゃあおれは一旦退いて……ってうおっ!」
レグルが後方に退くと、土の中から大口を開けた食虫植物が現れてサルヴァトルごとレグルを飲み込もうとする。
「ちょっと!あたしが仕掛けた罠を無駄にしないで!」
「知らないよ! それよりこいつを止めてくれ! 食われる!」
「その子は無理よ。獲物を食い殺すまで止まらないわ。」
君はレグルを飲み込もうとしている植物に向かって炎の攻撃魔法を放って焼き切る。
「おー、助かった。ありがとう、魔法使い。」
レグルがひと息ついたところに、すかさず魔物が襲い掛かってくる。
「ぼーっとするな、レグル! 危ない!」
フォルティスをまとったタイシが飛び込み、刃の羽根で魔物を両断する。
「いやー危ないところだった……ってうわ!」
レグル目がけて木が倒れてくる。君は咄嵯にレグルの周りに防御障壁を展開し、倒木の直撃を防いだ。
「タイシ、魔物と一緒に木まで斬るなよ。」
「いや、面目ない。木に囲まれているとどうにも飛びづらい。」
「……邪魔だから来ないでって言つたのに。」
ガーディアン・アーマー形態を解除したテーラが呆れたようにつぶやいた。
どうやら、残っていた魔物はすべてテーラが始末したようだ。
自分の持ち場だから戦い慣れているということもあるのだろうが、テーラの力が頭ひとつ抜けているように君の目には映った。
そんなテーラは、難しい顔をして君のことを見ている。
「あなた。ただの物好きって感じじゃない。本当に本物なの?
本物の英雄だと言って皆を統率すべきか。あるいは、単なる物真似だとおどけてみせるか。
どう立ち回っていいものか判断しかねるため、ご想像にお任せするよ、と言って曖昧に笑った。

「さて、魔物は片づけたけど、問題は解決していない。森の異変、テーラはどう見る?」
テーラは刈り取った奇妙な植物を見つめている。
「緑化がカリュプスの理性による人類への歩み寄りだとしたら、森の異変は何らかのメッセージとして見ることができる。
このあたりだけで起きている異変なのか、広域で起きている問題なのかを知る必要がある。今回のー件をガルデニアロッドに報告すべき。」
「そういえば、先日の魔物凶暴化の件。」
タイシの表情が曇った。
「テーラのレボートをガルデニアロッド評議会と共有しようと思ってデータを送ったんだけど………なにも返答がなかったんだ。」
「よくないことが起きてるのかもしれないにゃ。」
***
君たちは集落に戻り、ガルデニアロッドとの通信を試みるが、失敗に終わった。
通信は、重要拠点の小ロッドを経由してなされるらしい。
一晩経ってから改めて通信をいれてみるが、やはり反応はなかった。
ガルデニアロッドでなにか問題が起きたのか。あるいは中継のための小ロッドになにかあったのか。
「中継ロッド、6号ロッドに行ってみよう。」
意を決したように、タイシが切り出した。
「いいわね! 面白そうだわ!」
「おいおい……遊びじゃないんだぞ。」
「そういうタイシもちょっとうれしそう。僕の英雄譚が今――幕を開ける! デーン! とか思ってそう。」
「それはあるわね。絶対デーン! って頭の中で壮大な音が鳴ってるわよ。」
テーラが呆れたように大きなため息をつく。
「タイシ。あなたまでふざけてないで、他の小隊長たちと情報共有して。
私たちが抜けてこのロッドの防衛は回るのかどうか。」
「僕はふざけてないのに……。」
「あたしたちが抜けるのは大丈夫じゃないかしら?自警団ってわりとみんな暇そうにしてるもの。
熱心に魔物を殺してるのなんてあたしとあんたぐらいよ。」
「一緒にしないで。」
「ていうか、テーラ、一緒に来てくれるんだな。」
「あなたたちだけで遠出して死なれたら寝覚めが悪いから。」
「テーラって意外と面倒見いい?」
「……みんなを700号ロッドに縛りつけて、私ひとりでいってもいい。」
テーラは真顔で言った。冗談だろうが、本当にやりかねないとも思えた。

「なにが待ち受けているかわからないにゃ。みんなで行くにゃ。」
story最初の記憶
守れ。
強くなれ。
そんな〈声〉が夢の中で響いた。
毎度のことながら誰だよとレグルは思う。
そして、夢なのだから姿くらい見せればいいのにとも思う。
二度寝しようと思ったが、窓の外は朝日が昇っているようだ。
「……微妙な時間だな。
早起きになってしまうが(むしろそれに越したことはないのだが)、少し体を慣らしておこうと思い、レグルは着替えて外に出る。
「強くなれ、か。
我が心に眠る戦獣よ、救世の星となれ!¨サルヴァトル¨!
敵をイメージする。
めちゃくちゃでかい。脚が4本で腕が6本の半人半獣。向う脛を突いて、
ひるんだ隙を狙って腕をすべて斬り飛ばし、最後に首を刎ねるイメージ。
「はあっ!
レグルは見えない敵に向かって鋭い鈎爪の斬撃を続けざまに放った。
「寝起きにしては……まずまずじゃないか?
ささやかな自画自賛をしているとー―
傍らに、テーラが立っていた。
「朝から修練なんてらしくない。
「いやー、毎日やってるよ。おれの日課。
「嘘つき。この時間にレグルを見たことなんて1回もない。
「バレたか。なんか、早くに目が覚めちゃったんだよ。
普段だったら二度寝しているところを、今日に限って起き出したということは、旅立ちを意識しているのかもしれない。
「テーラはこのロットに来る前、どんなところにいたんだ?
「どこでもいいでしょ。レグルには関係ない。
「おれは覚えてないんだけどさ、ここじゃないどこかから来たらしいんだ。
3歳くらいのとき? 700号ロットの根元に捨てられてたんだって。すごくね?
「すごい……の? それって。
当時の記憶はほとんどなかった。
伝え聞くところによると、推定3歳児のレグルはとんでもない神童だったという。
物心がつくかつかぬかという時分に、ガーディアン・アーマーを展開していたらしいのだ。
あるいは捨てられていたのではなく、自らの意思でやってきた可能性もなくはない。
「そのときのことは、全然覚えてないけどなー。」
自我の芽生えとも言うべき最初の記憶は、『守りたい』「強くなりたい」という焦がれる想いだった。
しかし、『何を守りたいのか』『なぜ強くなりたいのか』については、さっぱり心当たりがなかった。
漢然と、この世界を守るために強くなりたいのだろうと解釈してみるが、しっくりこない。
何か。
何か、あった気がするのだ。
守らなくては、強くならなくてはと切に願うようになった理由が、何かあったはずなのだ。
守りたい。強くなりたい。ぼんやりとしながらも確かに存在する想いは、根の無い花のようだった。
謎の〈声〉についても、鶏が先か卵が先かという話だ。
守りたいという想いが〈声〉を生み出したのか、〈声〉の呼びかけによって想いが生じたのか。
いずれにせよ、レグルにとってはなんとも腑に落ちない、もやもやとした心持だ。
「そういえぱおれ、この集落から出るの初めてだ。」
何を守りたいのか、なぜ強くなりたいのか。
それさえ知ることができれば、自分はきっと立派に成長できると思った。
根拠はない。
「旅に出れば、なにかつかめそうな気がするな一。
「6号ロットに向かうのは遊びじゃない。自分探しの旅をするなら別行動でお願い。
「でもおれひとりだと死ぬかもよ? 寝覚めわるいよ?
「……卑怯者。」
story 破壊衝動

「なるほど、こんな感じか。
魔物が跋扈(ばっこ)する様を見ながら、アヴリオは満足げにつぶやく。
(思うままにのさばること。)
「本気を出せばあれを完全復活させることもできそう。だけど、相当無理をしないとだ。
無理をしては、意味がない。エネルギーの無駄遣いはやめよう。そう思うでしょう、メロウ?」
アヴリオは傍らのガーディアン・アバター、メロウに問いかける。
「しゃべらないの? 私の作り方が悪かったのかな。それとも、私の心自体が、よくないのかな?
なんにしても、寂しい。こう寂しいと、誰かにちょっかいだしたくなる。」
アヴリオの漂っていた視線が、魔物と戦う男をとらえる。
「おや?」

八つ当たりするように、あるいは親の仇を討つかのように、効率などとは程違い荒々しい戦い方をしていた。
俄然興味が湧いたアヴリオは、男のもとに向かった。
「ずいぶんと熱心なガーディアンだね。」
男は警戒心をむき出しにして、アヴリオと相対する。
臆病さゆえの攻撃性。男はその見本のような存在だとアヴリオは思う。

「ああ、いや、失礼。君はガーディアン? それとも人間?
あるいは……こういうことを面と向かって聞くのはマナー違反なんだろうか?
すまないね。このあたりのことを、よく知らないんだ。世間知らずを許してほしい。」
「……俺はガーディアンだ。」
男はしばし逡巡した後、慎重に言葉を選ぶように答えた。
「アバターをまとうような形態、ガーディアン・アーマーだっけ?やっぱり、強さが段違いなのかな?
それから、私のアバターが喋らないんだ。病気なのかな?」
男は盗み見るように、アヴリオとメロウに素早く視線を走らせる。
そんな男を、アヴリオは無遠慮に観察する。
「なにを言っている。喋らない個体もあるだろうが。」

「こんにちは。メロウは元気だよ。お前は元気ないの? 元気出したほうがいいよ。」

「おっと、喋った。私のは、喋る個体だったみたい。」
「私はアヴリオ。もしかして自己紹介も一般的ではないのかな。とことん田舎者で申し訳ない。」
「……俺はモルブだ。」
「つい最近になってやっとアバターを召喚できるようになったんだ。いろいろと、わからないことが多くてね。」
警戒心をむき出しにしていたモルブの表情が更に険しくなる。
「後天的にアバターを召喚したということは、お前人間か。」
「そんなのどっちでもいいじゃないか。この世界には素晴らしい言葉がある――」
「素晴らしい言葉、だと?」
「知らない?「大切なものを護ろうという心があれば、誰しも皆がガーディアンだ」ってね。」
「その言葉自体が間違いだ。口当たりのいい言葉で、ガーディアンと人間の共生で生じる問題をうやむやにしている。」
アヴリオのことを恐れるに足らない存在とみなしたのか、モルブの口からは滑らかに言葉が出てくるようになる。
「それはつまり、どういうこと?」
「人間がガーディアンを名乗ることはできても、ガーディアンがガーディアンであることからは逃れられない。それがこの世界だ。」
「君はこの世界が嫌いなの? それとも、人間が嫌い?」
「同義だ。こうなったのも、人間のエゴによるものだ。」
モルブから、激しい破壊衝動を感じた。
ガーディアンの原料がカリュプスと名付けられたあの生物であるという事実を、まざまざと見せつけられているようだ。
「人間のエゴ、と言ったね。これまた無知な田舎者で恐縮だけど、人間とガーディアンは今、仲良く共生しているんでしょう?」
「共生といっても、所詮は上辺だけだ。」
その感情は怒りか、憎しみか。警戒心を塗りつぶして隙だらけになってしまうほどに、モルブは昂っていた。
「そもそも人間はガーディアンのことを道具として生み出し、千年以上も利用してきたんだ。百年や二百年で認識が変わるとは思えん。」
モルブの破壊衝動をひしひしと感じる。肌で感じる感覚など、カリュプスのそれに酷似している。
ガーディアンを、カリュプスの代わりとして利用できないだろうか。
この男に力を与えた上で、操れば――
アヴリオの全身から波動が放たれる。
「ぐあっ!」
突然の光にモルブは顔をそむける。
どの程度正確に操れるものか。アヴリオは手始めにモルブの本能を刺激して、破壊衝動を最大限まで高めようとするが――
「なっ……!」
モルブの精神――ソムニウムがそれを跳ね除けた。
「すごい反発。びっくりして殺してしまうところだったよ。」
「メロウはびっくりしてないよ。でも、殺してしまうところだったよ。」
「お、お前……一体何をした……!モルブは苦悶の表情を浮かべ、うずくまる。」
突然流れ込んできた強大な力に馴染んでいないのだろう。
「なるほど。面白い。ガーディアンというものは本当によくできているんだね。人形や道具の類だろうと舐めていたよ。」
ガーディアンの自我は、想像以上に強固かつ複雑な構造をしているようだ。

「与えた力を返せなんて言わないよ。それは、はなむけだ。
思う存分、憎しみを人間にぶつけるといい。私はそれを、見てみたいな。」
「人間にぶつければいいとメロウは思うよ。骨はメロウが拾って食べてあげる。」

| 幻魔特区スザク | |
|---|---|
| 幻魔特区スザク 序章・1・2・3・4・5 | 2015 03/12 |
| 幻魔特区スザク 外伝 | 03/12 |
| 魔法使いとクロ犬のウィズ | 04/01 |
| 幻魔特区スザクⅡ ~カリュプスの槍~ | 2015 06/30 |
| 幻魔特区スザクⅡ 外伝 | 06/30 |
| ハッピースイーツカーニバル Story3 | 02/22 |
| キワム編(Christmas stories 2015) | 12/15 |
| 幻魔特区スザクⅢ ~ソムニウムの輝き~ 序章 1 2 3 4 外伝 | 2016 05/31 |
| アッカ編(Christmas stories 2016) | 12/14 |
| キワム&ヤチヨ編(6th Anniversary) | 2019 03/05 |
| キワム&クロ編(サマコレ2020) | 06/30 |
黒猫ストーリーに戻る
白猫 mark